「みなづちブログ」はリンクフリーです。リンクを行う場合の許可や連絡は不要です。引用する際は、引用元の明記と該当ページへのリンクをお願いします。
額から血がにじむまで頭を下げても「他人」:50年連れ添った同性パートナーが看取りから排除される国、日本
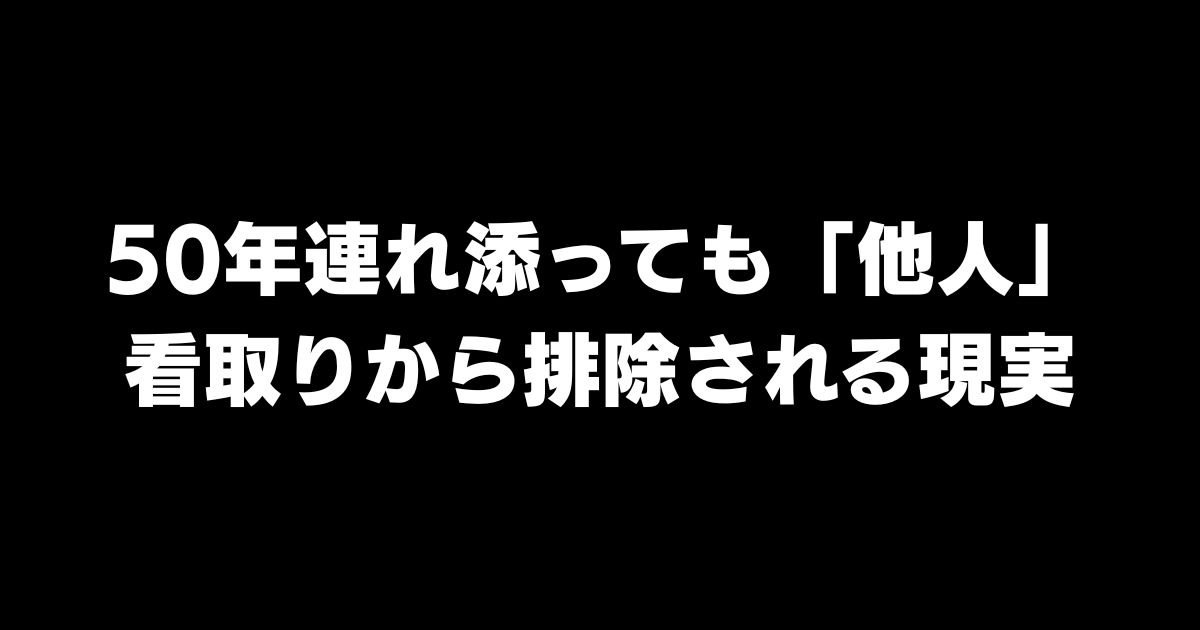
ゲイのみなづち(@minaduchi)です。
人生の最期に、愛する人の手を握ること。それは誰にとっても当たり前の権利だと思っていないだろうか。
しかし日本では、50年連れ添ったパートナーでも「法的に他人」として、その最期の瞬間から排除される人々がいる。
婚姻届を出せないという、ただそれだけの理由で。
異性カップルなら、出会って3年でも、1年でも、婚姻届を出せば「家族」として認められる。危篤の知らせを受ければ、当然のように病室に入れる。医師から説明を受け、最期の瞬間に立ち会い、手を握ることができる。
では、50年連れ添った同性カップルは?
答えは「法的に他人」だ。どれだけ長く一緒に暮らしても、どれだけ深く愛し合っても、法律の前では赤の他人として扱われる。
今回は、介護現場を想定した事実に基づく再構成ストーリーと、実際の法的データをもとに、この問題を考えたい。
規則が愛を引き裂く状況、そしてなぜ施設側が「拒否せざるを得ない」のか、その背景にある制度の問題を。
本記事のポイント
- 50年連れ添っても「法的に他人」扱い
- 施設が拒否する背景には法的リスクがある
- パートナーシップ制度に法的拘束力なし
- 6件中5件の高裁が違憲判断を示した
- 制度が変われば、現場も変わる
記事を書いている人のプロフィール

- 僕はゲイ×強迫性障害
- ノンケ→バイ→ゲイに心変わりしてきた
- ゲイを自覚して20年ほど
- Instagramを中心に発信活動しているクリエイター
- 🌈 結婚する自由を、すべての人に。
50年の愛が「規則」に負けた日
特別養護老人ホームで働く介護士がいた。担当していたのは80歳の男性。認知症の末期で、家族の顔も名前も分からなくなっていた。ただ一つだけ、彼が繰り返し呼び続ける名前があった。「ミナヅチ」。誰なのか、職員の誰も知らなかった。
認知症末期でも呼び続けた名前
毎日のように、彼は「ミナヅチ」と泣き叫んだ。食事の時も、入浴の時も、夜中に目を覚ました時も。
家族すら認識できないのに、その名前だけは決して忘れなかった。
50年という歳月が刻み込んだ記憶は、認知症でさえ消すことができなかったのだ。
危篤、そして駆けつけた「他人」
ある日、容態が急変した。危篤状態。
すると、一人の男性が施設に駆けつけてきた。息を切らせながら、彼は言った。
「僕がミナヅチです」
50年間、ずっと一緒に暮らしてきたパートナーだった。
しかし、法的には「他人」。婚姻届を出すことができない二人に、法律は何の保護も与えていなかった。
額から血がにじむまで頭を下げた
ミナヅチさんは施設長に懇願した。最期だけでも、彼のそばにいさせてほしいと。
しかし、施設長の答えは冷たかった。「家族のみです。規則ですから」
ミナヅチさんは頭を下げた。額を床に押しつけ、何度も何度も頭を下げた。額にあざができるまで、彼は懇願し続けた。
「50年一緒にいたんです。最期だけでも、お願いします」
それでも答えは変わらなかった。「規則は絶対です」
50年の愛が、たった一言の「規則」の前で立ちすくんだ瞬間だった。
規則と尊厳のはざまで
このような状況で、施設職員はどう判断すべきなのか。規則と人間の尊厳のはざまで、多くの現場が葛藤を抱えている。
ある介護士は、その葛藤の末に、ミナヅチさんを居室に案内した。
ミナヅチさんが彼の手を握った瞬間、奇跡が起きた。ずっと苦しそうだった表情が、ふっと和らいだ。
「ミナヅチ…やっと会えた」
安らかな笑顔を浮かべて、彼は息を引き取った。
この介護士の行動は、職業倫理の観点から議論の余地がある。
しかし、そもそも「50年連れ添ったパートナーを他人として扱う」という規則自体が、人間の尊厳を踏みにじっているのではないか。
「法的に他人」が奪うもの
なぜ50年連れ添ったパートナーが「他人」として扱われるのか。それは日本に同性婚がなく、パートナーシップ制度にも法的拘束力がないからだ。この制度の限界を正確に理解することが、問題の本質を知る第一歩になる。
パートナーシップ制度の現状
2025年5月末時点で、パートナーシップ制度を導入している自治体は532に達し、人口カバー率は92%超、登録件数は9,837組に上る(渋谷区×認定NPO法人虹色ダイバーシティ共同調査)。
数字だけ見れば、日本も変わりつつあるように見えるかもしれない。しかし、この制度には決定的な限界がある。
法的拘束力がないという現実
パートナーシップ制度は、自治体による「象徴的な認知」に過ぎない。法的地位を与えるものではない。
具体的に何が欠けているのか。
提供されないもの:
- 相続権なし(法定相続人になれない)
- 税制優遇なし(配偶者控除が使えない)
- 社会保障なし(遺族年金、健康保険の被扶養者認定なし)
- 医療同意権なし(法的権限なし)
- 自治体外では効力なし
税制上の格差を正確に理解する
異性婚カップルが受けられる配偶者控除は、所得税で最大38万円、住民税で最大33万円、合計で最大71万円の所得控除となる。
ここで重要なのは、これは「控除額」であり「節税額」ではないという点だ。
実際の節税額は、その人の所得税率によって変わる。たとえば所得税率20%の人なら、38万円の控除で約7.6万円の節税になる。
いずれにせよ、同性カップルはこの控除に自動的にはアクセスできない。法的婚姻が認められていないからだ。
「お願いベース」の脆さ
パートナーシップ制度は、病院や企業に法的義務を課さない。すべては相手の「善意」に依存する「お願いベース」の制度だ。
理解ある病院なら面会を認めてくれるかもしれない。しかし、「規則は規則」と言われれば、それまで。50年の愛も、法律の前では無力になる。
なぜ施設は「家族のみ」と言うのか
ストーリーの中で、施設長は「規則は絶対です」と言った。冷たく聞こえるかもしれない。しかし、施設側にも「拒否せざるを得ない理由」がある。問題の本質は、施設の対応ではなく、施設をそのような判断に追い込んでいる制度にある。
法的リスクの回避
介護施設や病院には、入居者・患者のプライバシーを守る法的義務がある。
「法的に他人」である人に情報を開示したり、面会を許可したりすると、後から親族がクレームを入れてくるリスクがある。
「なぜ赤の他人を病室に入れたのか」「勝手に情報を漏らしたのではないか」。
そう訴えられた場合、施設側には法的な防御手段がほとんどない。
パートナーシップ証明書があっても、それは法的拘束力を持たないからだ。
同意権と責任問題
医療や介護の現場では、治療方針や処置について「同意」が必要になる場面が多い。
法的な配偶者や親族であれば、その同意には法的根拠がある。
しかし、同性パートナーには医療同意権がない。
万が一、パートナーの同意に基づいて処置を行い、後から親族が「そんな同意は無効だ」と主張した場合、施設や医療者が責任を問われる可能性がある。
遺産・相続トラブルの懸念
高齢者の看取りの場面では、遺産や相続の問題が絡むことも多い。
施設側は、親族間(あるいは親族とパートナー間)のトラブルに巻き込まれることを避けたい。
法的に「他人」であるパートナーを面会させたことで、後から「不当な影響を与えた」「遺言を書き換えさせた」などと主張される可能性もゼロではない。
施設にとって、最も安全な選択は「法的な家族のみ」というルールを厳格に適用することになる。
現場スタッフの判断権限
実際に対応するのは現場のスタッフだが、彼らには個別の判断を下す権限がないことが多い。
マニュアルに「家族のみ」と書かれていれば、それに従うしかない。
「50年連れ添ったパートナーです」と言われても、それを証明する法的書類がない。
パートナーシップ証明書を見せられても、「これは法的拘束力がありません」と説明されている。
現場スタッフは、善意で判断する権限を与えられていないのだ。
施設を責めても問題は解決しない
ここで重要なのは、施設や職員を責めても根本的な解決にはならないということだ。
彼らは、現行の法制度の中で、リスクを最小化しようとしているに過ぎない。
問題の根本は、50年連れ添ったパートナーを「法的に他人」として扱う制度そのものにある。
同性婚が認められれば、パートナーは自動的に「配偶者」となる。
配偶者であれば、面会も、医療同意も、情報開示も、すべてが当然の権利として保障される。
施設側も、リスクを気にすることなく、人間として当たり前の対応ができるようになる。
制度が変われば、現場も変わる。
83.3%が違憲判断、それでも変わらない現実
では、司法はこの問題をどう見ているのか。2024年から2025年にかけて、6つの高等裁判所で同性婚をめぐる判断が示された。結果は明確だ。5件が違憲、1件が合憲。実に83.3%の高裁が、現行制度は憲法に違反すると判断した。
6件の高裁判決
| 裁判所 | 日付 | 判決 |
|---|---|---|
| 札幌高裁 | 2024年3月14日 | 違憲 |
| 東京高裁(1次) | 2024年10月30日 | 違憲 |
| 福岡高裁 | 2024年12月13日 | 違憲 |
| 名古屋高裁 | 2025年3月7日 | 違憲 |
| 大阪高裁 | 2025年3月25日 | 違憲 |
| 東京高裁(2次) | 2025年11月28日 | 合憲 |
札幌高裁は憲法24条1項・2項と14条1項の違反を認定。福岡高裁は憲法13条(幸福追求権)の違反まで踏み込んだ。司法のメッセージは明確だ。「今の制度は、憲法が保障する平等に反している」。
唯一の「合憲」判決
2025年11月28日、東京高等裁判所(東亜由美裁判長)が唯一の合憲判断を示した。
原告の一人は「悪夢のような判決」と語り、「この怒りを力に変えて、最高裁では笑顔でよい判決を勝ち取りたい」と述べた。
弁護団は「性的マイノリティに対する誤解と偏見に満ちた、特異な判決」と厳しく批判した。
最高裁での統一判断へ
6件すべてが最高裁に上告されており、2026年から2027年にかけて統一判断が示される見込みだ。
83.3%の高裁が違憲と判断した制度。
それでも今日この瞬間も、50年連れ添ったパートナーが「他人」として扱われ、愛する人の最期に立ち会えない現実が続いている。
私たちにできること
制度を変えるには、声を上げ続けるしかない。
具体的なアクション:
- 署名活動に参加する
- 選挙で候補者の政策を確認する
- SNSで情報を共有する
- 家族や友人と話し合う
- 地元の議員に意見を届ける
小さな行動の積み重ねが、やがて大きなうねりになる。
最高裁の判断は2026年から2027年に示される見込みだ。私たちの声は、確実に届いている。
まとめ:愛を守る法律を、この国にも
50年連れ添っても「他人」。額から血がにじむまで頭を下げても「規則は絶対」。これが、2025年の日本の現実だ。
しかし、施設を責めても問題は解決しない。彼らは現行制度の中でリスクを最小化しようとしているだけだ。
問題の根本は、50年のパートナーを「法的に他人」として扱う制度そのものにある。
6件中5件の高等裁判所が違憲と判断した。83.3%の司法が「この制度はおかしい」と声を上げている。それでも、法律は変わっていない。
しかし、希望はある。若い世代の約8割が同性婚に賛成している。経済界も多様性の観点から法整備を求めている。そして何より、最高裁での統一判断が近づいている。
制度が変われば、現場も変わる。施設も、病院も、リスクを気にすることなく、人間として当たり前の対応ができるようになる。
愛する人の最期に手を握ること。
それは、すべての人に保障されるべき権利だ。愛を守る法律を、この国にも。その日が来ることを、私は信じている。
この記事の元になった投稿はこちら:
Threadsで見る
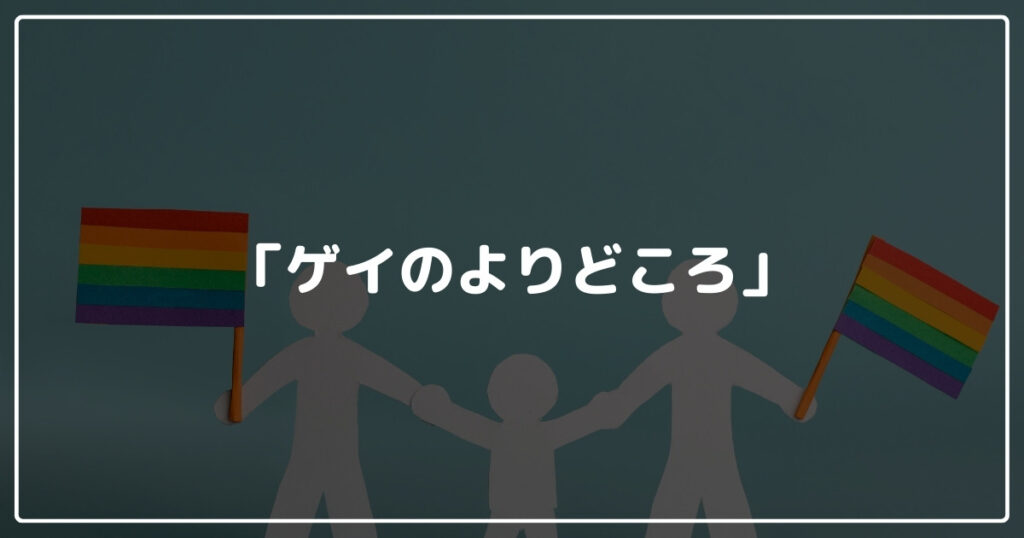


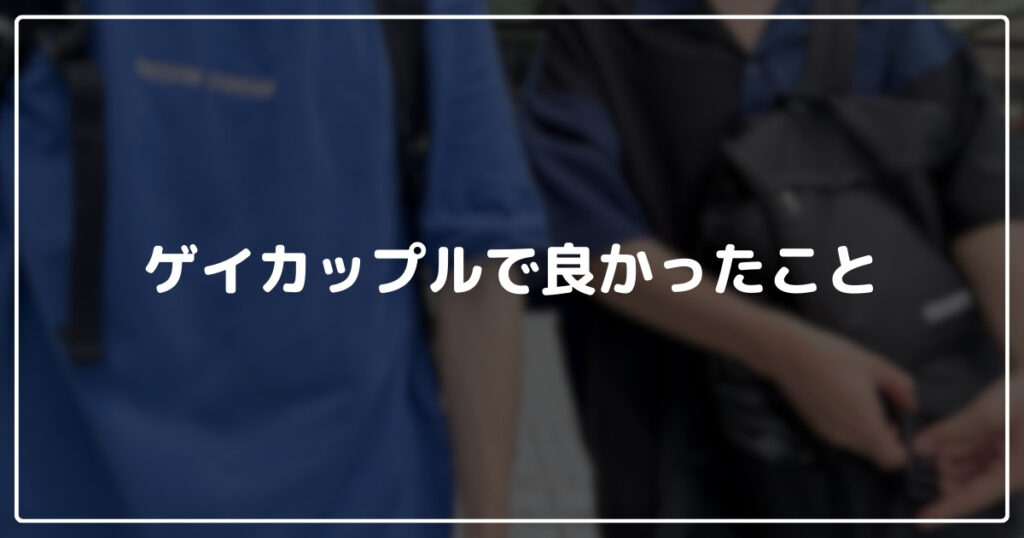

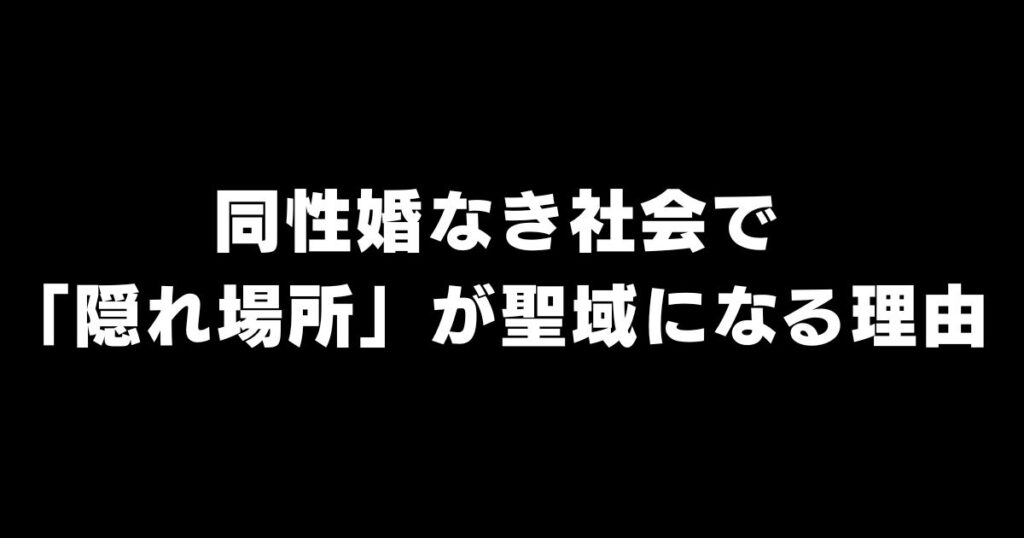

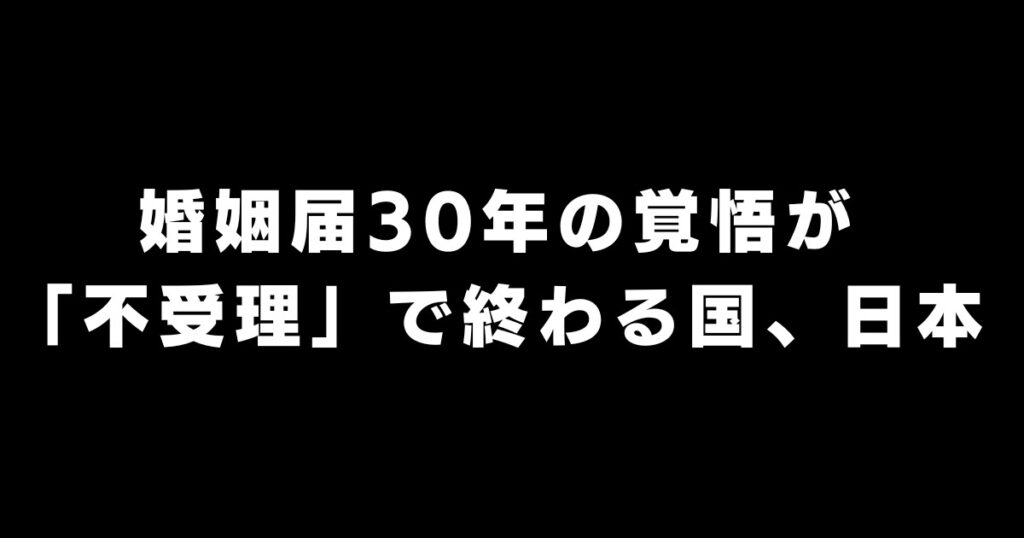
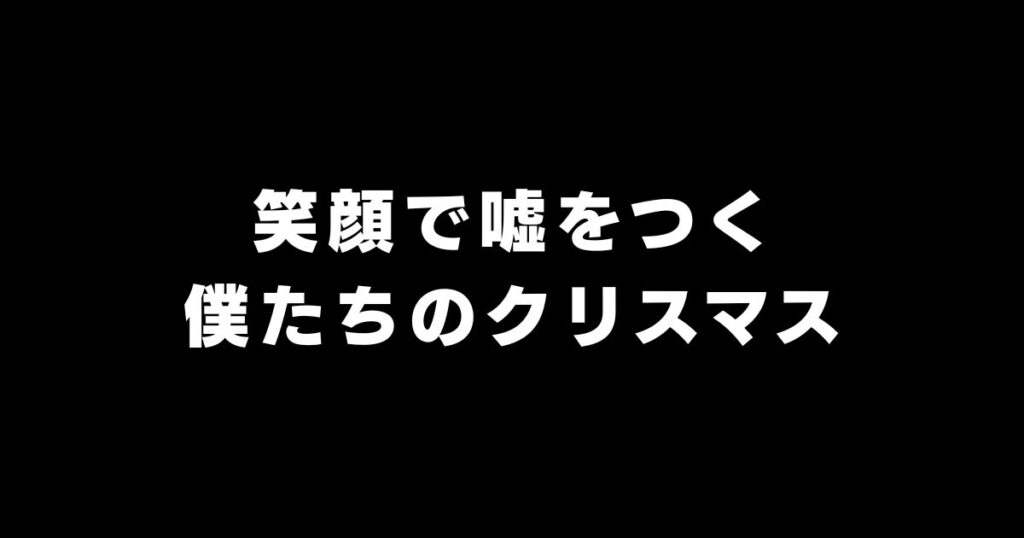
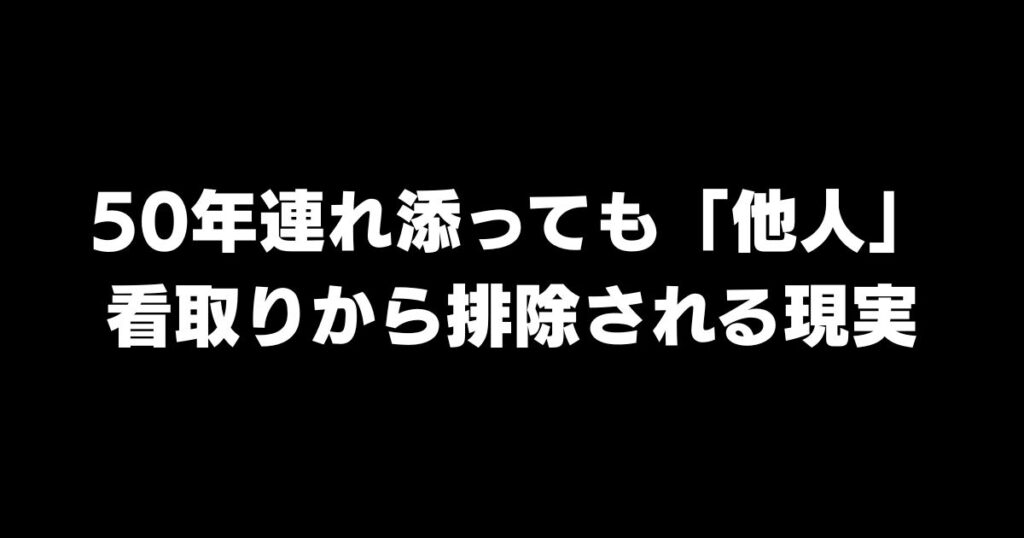

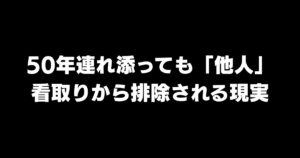
コメントお気軽にどうぞ!