「みなづちブログ」はリンクフリーです。リンクを行う場合の許可や連絡は不要です。引用する際は、引用元の明記と該当ページへのリンクをお願いします。
同性婚と「外圧」、日本が変わるとき、いつも外からの力があった
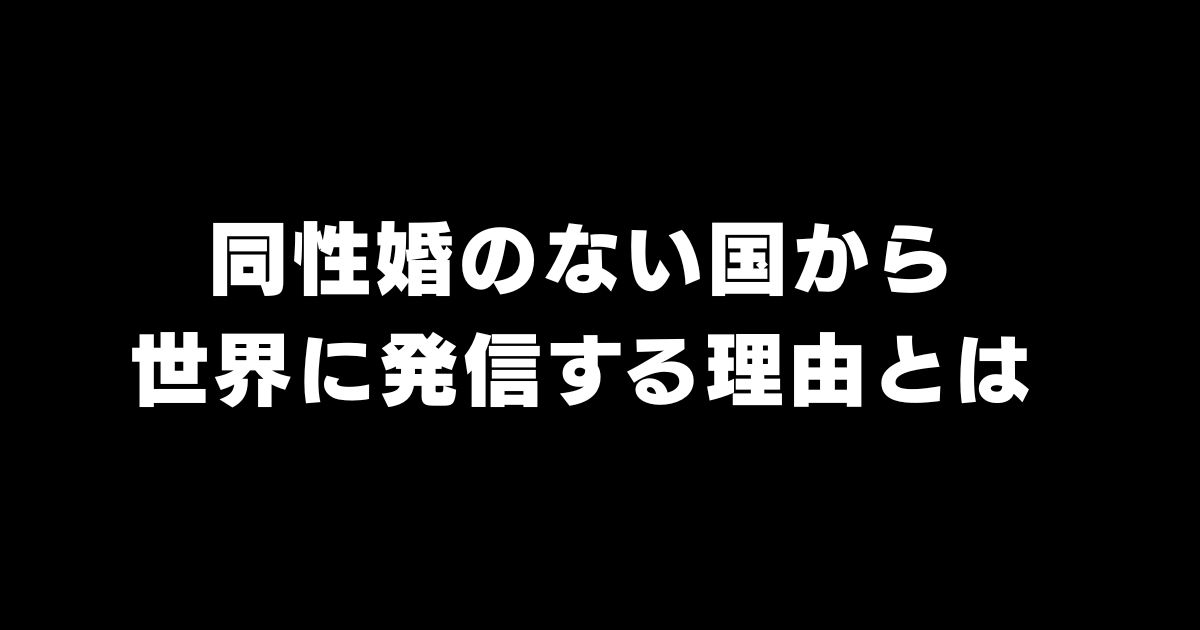
ゲイのみなづち(@minaduchi)です。
日本はG7で唯一、同性カップルに対する国レベルの法的保護制度を持たない国です。
全国6つの高等裁判所のうち5つが「違憲」または「違憲状態」と判断し、世論調査では約6〜7割が同性婚に賛成しています。それにもかかわらず、国会は30年近く動いていません。
「外圧でしか変われない国」という言葉があります。
しかし日本の法制度改革の歴史を振り返ると、外からの力が変革の触媒として機能してきた事実が浮かび上がってきます。
1985年の男女雇用機会均等法、2014年のハーグ条約加盟、2023年のLGBT理解増進法。いずれも国際的な圧力や視線が、国内の膠着状態を打破するきっかけになったとされています。
「外圧」は恥ではなく、変革のための戦略的資源になり得るのです。
この記事では、日本の法制度改革における外圧の歴史的役割を検証し、同性婚実現に向けて何を学べるのかを考えていきます。
本記事のポイント
- 日本の重要な法制度改革の多くは「外圧」がきっかけで実現してきた
- 男女雇用機会均等法、ハーグ条約、LGBT理解増進法に共通するメカニズムがある
- イタリア、台湾、タイの成功事例から日本が学べる具体的な戦略がある
- 「外圧」を戦略的に活用することで同性婚実現に近づける可能性がある
記事を書いている人のプロフィール

- 僕はゲイ×強迫性障害
- ノンケ→バイ→ゲイに心変わりしてきた
- ゲイを自覚して20年ほど
- Instagramを中心に発信活動しているクリエイター
- 🌈 結婚する自由を、すべての人に。
同性婚30年、「外圧でしか変われない国」と呼ばれて

国内の議論だけでは動かなかった政策が、国際社会からの圧力をきっかけに動き出す。この現象は、同性婚を求める当事者にとって、苦しみであると同時に、戦略的な希望でもあります。
30年、待った
1990年代から、日本でも同性カップルの権利について議論が始まりました。
しかし30年が経っても、国レベルの法整備は実現していません。
地方自治体のパートナーシップ制度は530を超え、人口カバー率は92.5%に達しました。
それでも、これらの制度には法的拘束力がありません。
相続権も、配偶者控除も、遺族年金も、原則として対象外のまま。
国会議員に手紙を書きました。
署名を集めました。
デモにも参加しました。
それでも、法律は変わりませんでした。
「売国奴」と呼ばれても
ある日、私は決意しました。
英語で発信を始めよう、と。
日本の現状を、世界に伝えよう、と。
「外圧に頼るのか」「売国奴だ」という声が聞こえてきます。
正直に言えば、私自身もその言葉に傷つくことがあります。
できることなら、日本が自分の力で変わってほしかった。
でも、30年待っても変わらなかったのです。
私にはもう、時間がありません。
世界に向けて、書き始める
“Japan is a beautiful country? Maybe. But it’s the ONLY G7 nation without same-sex marriage.“
私はこう書きました。
これは批判ではありません。
事実です。
G7の中で、同性カップルに対する国レベルの法的保護制度がないのは、日本だけ。
この事実を、世界中の人に知ってもらいたい。
そして、国際社会の目が日本に向くことで、変化のきっかけが生まれることを願っています。
同性婚と「外圧」:なぜ日本で機能するのか

日本では「外圧」が法制度改革の強力な触媒として機能してきました。しかし、なぜ外圧なのでしょうか。国内で声を上げるだけでは、なぜ不十分なのでしょうか。この疑問に答えるために、国際政治学の知見を借りてメカニズムを解説していきます。
なぜ国内の訴えだけでは動かないのか
30年間、当事者たちは声を上げ続けてきました。署名活動、デモ、ロビイング。
それでも国会は動きません。世論調査では約6〜7割が賛成し、高裁の大多数が違憲と判断しているにもかかわらず、です。
この「動かなさ」には構造的な理由があります。
国内の利害関係者(保守派、宗教団体、一部政治家)が強固な抵抗勢力を形成し、政治家は「票にならない」と判断して動かない。いわば、国内の力学だけでは均衡状態が崩れないのです。
では、どうすればこの均衡を崩せるのか。ここで「外圧」という変数が重要になってきます。
「反応国家」としての日本
国際政治学において、日本はしばしば「反応国家(Reactive State)」と呼ばれてきました。
これは、自律的な外交戦略よりも、外部環境の変化や他国からの圧力に対して受動的に適応する傾向を指す学術用語です。
この特性は、必ずしも否定的なものではありません。むしろ、国際社会の規範や基準を取り入れることで、国内の既得権益や岩盤規制を打破する「窓」として機能してきた側面があります。
明治維新における不平等条約改正から、現代のTPP交渉に至るまで、日本の近代化の歴史は、外部からの刺激を内部変革のエネルギーに変換してきた歴史でもあります。
同性婚についても、この「反応国家」の特性を戦略的に活用することが有効な選択肢となり得るでしょう。
「ブーメラン・パターン」という戦略
国内で直接訴えても動かない場合、どうすればいいのか。
国際政治学者のケックとシッキンクは、この問いに対する答えを提示しています。彼らが提唱した「ブーメラン・パターン」という理論は、まさにこの状況を説明するものです。
ブーメランを投げると、一度遠くに飛んでから手元に戻ってきます。
同じように、国内で投げた声を一度「国際社会」に届け、そこから圧力として戻ってくる形で政府を動かす。これが「ブーメラン・パターン」の基本的な考え方です。
具体的な流れは以下の通りです。
まず国内の当事者や支援者が、英語などで情報を発信します。
次に国際NGOや海外メディアがそれを取り上げ、国連の人権機関や他国政府が日本に勧告や懸念を表明する流れとなります。
その国際的な圧力が、国内の議論を活性化させます。メディアが報道し、世論が動き、最終的に政府が対応を迫られる。同性婚を巡る日本の状況は、まさにこのパターンが適用可能な典型例と言えるでしょう。
「名誉」と「恥」の外交心理学
日本政府が外圧に反応する際、その深層心理には「国際社会における名誉ある地位」への渇望があるとされています。
そして、そこから脱落することへの強い不安も存在します。
G7の中で日本だけが人権基準を満たしていないという事実は、単なる政策の違いではありません。
国家の品格に関わる問題として認識される傾向が強いのです。
「ネーミング・アンド・シェイミング(名指しと恥辱)」と呼ばれるこの効果は、日本のような国際的評価を気にする国において特に有効とされています。
ただし、過度な圧力はナショナリズム的な反発を招くリスクもあります。
効果的な外圧とは、「日本が国際社会で尊敬されるリーダーであり続けるために必要なステップ」として人権擁護を位置づけるものである必要があるでしょう。
同性婚の先例:男女雇用機会均等法とCEDAW

1985年の男女雇用機会均等法は、外圧が日本の法制度改革を動かした最も象徴的な事例です。この法律は、国連の女子差別撤廃条約(CEDAW)批准という国際公約がなければ、成立が困難だったとされています。同性婚を求める運動にとって、この歴史は重要な先例となります。
膠着状態だった国内議論
1980年代以前の日本において、女性労働者は法的に明確な差別的取り扱いを受けていました。
労働基準法の「母性保護」規定は、女性の職域を著しく制限する根拠となっていたのです。
当時の国内議論は完全に行き詰まっていました。労働組合や女性団体が差別の撤廃を求める一方、経営者側は「日本的雇用慣行」の維持を盾に強硬な抵抗を続けます。
「女性の保護規定を撤廃すれば、日本社会の美徳である家庭の安定が崩れる」という主張が繰り返されました。
「企業の活力が削がれる」という反論も根強く存在したのです。国内の力学だけでは、実効性のある平等法の制定は困難な状況だったとされています。
「国連女性の10年」という期限
この膠着状態を打破したのが、1979年に国連総会で採択された女子差別撤廃条約(CEDAW)でした。
日本政府は1980年に同条約に署名し、「国連女性の10年」最終年のナイロビ会議(1985年)までに批准することを国際公約として掲げたのです。
条約を批准するためには、国内法を条約の基準に合致させる必要がありました。これにより、国内法の整備は「望ましい目標」から「回避不可能な外交的責務」へと性質を変えます。
労働省の官僚たちは、CEDAW批准という錦の御旗を掲げることで、反対する経営者側を説得したとされています。
「国際社会の一員として、条約を批准できないことは許されない」という論理が、国内の抵抗を封じ込める武器となったのです。
不十分でも「扉を開けた」意義
制定当初の男女雇用機会均等法は、募集・採用・配置・昇進について事業主に「努力義務」を課すのみでした。罰則規定も欠いており、実効性には多くの疑問が呈されたのです。
しかし、重要なのは「法が存在する」という事実を作ったことでした。
一度法律ができれば、その後の改正への道が開かれます。実際、1997年には努力義務から禁止規定への強化が行われました。2006年改正(2007年4月施行)では間接差別の禁止も導入されています。
外圧は、最初の最も重い扉をこじ開けるための「バール」として機能したと言えるでしょう。
この事例は、同性婚運動にとって重要な示唆を与えています。最初から完璧な法律を求めるのではなく、まず「法的な枠組み」を作ることが、その後の改善への第一歩となり得るのです。
同性婚への示唆:ハーグ条約とG7圧力

2014年のハーグ条約加盟は、「G7で唯一」という事実が日本政府の意思決定に決定的な影響を与えた事例です。現在の同性婚を巡る状況と構造的に類似しており、最も参考になる先例かもしれません。
「子供の連れ去りのブラックホール」
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)は、国際結婚が破綻した際の子供の取り扱いについて定めた条約です。
日本では、国際結婚の破綻後、日本人の親が海外に住む配偶者の同意なく子供を日本に連れ帰る事例が多発していました。
日本国内の法感覚では、これは「DVからの避難」として理解されることもありました。しかし、欧米諸国の法体系においては、共同親権の侵害であり、明確な「誘拐」と見なされたのです。
FBIが日本人女性を指名手配する事態にまで発展しました。日本は国際社会から「子供の連れ去りのブラックホール」という不名誉なレッテルを貼られたのです。
北朝鮮の拉致問題を国際社会に訴えている日本が、逆に「拉致国家」と呼ばれる皮肉な状況でした。
米国議会と首脳級の圧力
この問題における外圧は、複数のレベルで同時に作用しました。まず、子供を連れ去られた海外の親たちが、それぞれの母国政府や議員に対して激しいロビイングを行ったのです。
米国議会では公聴会が開催され、被害当事者の証言を通じて日本政府が厳しく糾弾されました。2011年には、当時のヒラリー・クリントン国務長官が日本の外相に対し、条約加盟を強く求めるという首脳級の圧力が加えられたのです。
日本国内では、条約加盟に対する慎重論も根強くありました。弁護士会やDV被害者支援団体からは、「DV加害者の元へ子供を返還することを強制されるのではないか」という懸念が強く主張されていたのです。
外交的メンツが動かした決断
最終的に政府が条約加盟を決断した決定打は、「G7の中で日本だけが条約に未加盟である」という事実がもたらす外交的損失への恐怖だったとされています。TPP交渉などの重要局面において、日本が「法の支配」を尊重しない国と見なされることは国益を損なうと判断されたのです。
この事例から学べることは明確です。
「G7で唯一」という事実は、日本政府にとって無視できない外交的プレッシャーになり得ます。
同性婚についても、G7で唯一法的保護がないという事実を国際社会に広く認知させることで、政府を動かす力になる可能性があります。
実際、ハーグ条約加盟後も、国内法の運用において一定の配慮がなされています。外圧によって導入された制度でも、国内の実情に合わせた運用は可能なのです。
同性婚に最も近い事例:LGBT理解増進法

2023年6月に成立したLGBT理解増進法は、同性婚運動にとって最も直近かつ最も関連性の高い「外圧」事例です。内容的には当事者団体が求めていた「差別禁止」から大きく後退しましたが、この法律が成立した経緯には、外圧のメカニズムが明確に作用しています。
エマニュエル大使の「異例の外交」
2023年のG7広島サミットを前に、ラーム・エマニュエル駐日米国大使は、かつてないほど公然とした形で日本のLGBTQ政策への介入を行いました。
彼は自身のSNSを活用し、G7各国の駐日大使らと共に「日本は変わるべき時だ」と訴えるビデオメッセージを発信したのです。
また、当時の岸田首相に対し差別禁止法の制定を求める書簡を送付するなど、従来の外交儀礼の枠を超えた「パブリック・ディプロマシー(広報外交)」を展開しました。
この行動は、日本国内の保守派から「内政干渉である」との反発を招いたのです。
しかし、政治学的な観点から見れば、この働きかけは閉塞していた自民党内の議論を強制的に活性化させる効果があったとされています。エマニュエル大使の発言がメディアで大きく取り上げられることで、LGBTQの権利問題が「外交問題」へと格上げされたのです。
経済界からの「内なる外圧」
この局面で特筆すべきは、ACCJ(在日米国商工会議所)や経団連といった経済団体が、強く法整備を求めたことです。
彼らは人権の観点だけでなく、経済的合理性に基づいて提言を行いました。
「LGBTQフレンドリーでない日本は、優秀なグローバル人材を惹きつけられない」という主張は説得力を持っていました。これは、「人権 vs 伝統」という対立軸を「成長戦略 vs 停滞」という対立軸にずらす効果があったのです。
保守的な政治家に対しても説得力を持つ「新しい外圧」の形と言えるでしょう。
人権という抽象的な価値よりも、経済的利益という具体的な価値の方が、政策決定者を動かしやすい傾向があります。
不十分でも「最初の一歩」
成立したLGBT理解増進法は、「不当な差別はあってはならない」という曖昧な文言に留まりました。差別禁止や罰則規定は含まれておらず、当事者団体からは「後退した内容だ」との批判も出たのです。
しかし、この法律が成立した最大の要因は、G7サミットという「外圧のタイムリミット」が存在したことに他なりません。岸田政権は、サミットのホスト国として「何の成果もなしに各国のリーダーを迎えることはできない」という外交的メンツを守るために、法案成立を急いだとされています。
これは、男女雇用機会均等法の時と同様のパターンです。
「不十分な形であれ、まずは制度を作ることが優先された」事例であり、外圧がなければ法案の提出すら見送られていた可能性が指摘されています。
この法律を足がかりに、次は「差別禁止」へ、そして「同性婚」へと進むことが期待されます。
世界が変わった瞬間:イタリア、台湾、タイと同性婚

日本と同様の課題を抱えていた国々が、どのようにして変化を実現したのか。イタリア、台湾、タイの事例は、日本の同性婚運動にとって貴重な教訓を提供しています。それぞれの国が直面した困難と、それを乗り越えた戦略、そして日本が学ぶべき具体的な示唆を見ていきましょう。
イタリア:欧州人権裁判所が開けた扉
日本と同様にG7メンバーでありながら、カトリック教会の総本山を抱えるイタリアは、長らく西欧諸国で唯一、同性カップルへの法的保障を持たない国でした。国内では保守派やカトリック勢力の反対により、同性パートナーシップ法案は何度も廃案に追い込まれていたのです。
この政治的不作為を打ち破ったのが、2015年の欧州人権裁判所による「オリアリ判決」でした。裁判所は、イタリア政府が同性カップルに法的な承認と保護を与えていない現状は、欧州人権条約第8条(私生活及び家族生活の尊重)に対する違反であると断じたのです。
当時のレンツィ首相は「イタリアは欧州の恥である」というレトリックを用い、議会内の反対派を封じ込めました。
彼は法案成立のために「信任投票」という強硬手段を選択します。法案が否決されれば内閣総辞職となる賭けでしたが、国際司法機関の判決という正当性がバックボーンにあったからこそ可能な政治的決断でした。
2016年に成立した「シビル・ユニオン法」は、同性婚そのものではありません。養子縁組の権利も削除されるなど、保守派への譲歩を含んだものでした。しかし、G7諸国の中で「唯一法的保障がない国」という状態を脱したことの意義は大きかったのです。
【日本への示唆】 イタリアの事例は、「国際司法機関の判断」が国内政治を動かす強力なてこになり得ることを示しています。日本には欧州人権裁判所のような機関はありませんが、国内の高裁判決(6件中5件が違憲判断)という司法の声を、国際社会に発信することで同様の効果を生み出せる可能性があります。
台湾:外交的生存戦略としての同性婚
2019年にアジアで初めて同性婚を法制化した台湾の事例は、日本のアクティビストにとって希望の光です。同時に、日本の停滞を際立たせる鏡でもあります。
台湾における同性婚実現のプロセスでは、2017年の司法院大法官会議(憲法裁判所に相当)による違憲判断が決定的でした。
注目すべきは、この判断において国際的な人権基準や諸外国の立法例が積極的に引用されたことです。
台湾にとって同性婚の実現は、単なる人権問題を超えた高度な外交戦略でもありました。中国との対比において「民主主義、自由、人権を尊重する国」としてのアイデンティティを国際社会に示す必要があったのです。国際的な孤立を防ぐための生存戦略として、人権先進国というブランドが不可欠だったと言えるでしょう。
日本は台湾のような外交的孤立の危機には直面していません。しかし、「アジアの民主主義のリーダー」を自任するならば、台湾やタイに先を越された現状をどう受け止めるべきでしょうか。
【日本への示唆】 台湾は「人権先進国」というブランドを外交資源として活用しました。日本も同様に、同性婚の法制化を「国際社会でのリーダーシップ強化」という文脈で位置づけることが有効です。特に、中国や北朝鮮の人権問題を批判する立場にある日本が、国内の人権課題を放置していることの矛盾を指摘する声は、国際社会で説得力を持ちます。
タイ:経済成長のための人権
2024年に東南アジアで初めて「結婚平等法」が成立し、2025年1月に施行されたタイの事例も示唆的です。
タイは仏教国であり、伝統的な価値観が根強い社会です。それでも同性婚の法制化に踏み切った背景には、明確な戦略がありました。
タイ政府は、LGBTQフレンドリーな国としてのイメージを国際戦略として活用しました。観光産業の振興、海外からの投資呼び込み、さらには国連人権理事会理事国への選出を目指す意図があったとされています。
これは「経済成長のための人権」というナラティブが、保守層を含む広範な支持を得るために有効であることを示しています。
【日本への示唆】 タイの事例は、「人権 vs 伝統」という二項対立を避け、「経済的利益」という共通言語で保守層を説得する戦略の有効性を示しています。日本においても、「グローバル人材の獲得」「国際競争力の強化」「インバウンド観光の促進」という経済的観点から同性婚の必要性を訴えることは、政策決定者を動かす説得力のあるアプローチとなり得るでしょう。経団連やACCJがLGBT理解増進法を支持したのも、まさにこの論理に基づいています。
よくある質問(FAQ)

同性婚と「外圧」について、よく聞かれる疑問にお答えします。これらの疑問は、多くの方が感じる自然な反応であり、真剣に向き合うべき問いかけです。
「外圧」という言葉に抵抗を感じる方もいらっしゃるでしょう。「自分の国のことは自分で決めるべきだ」という感覚は、ごく自然なものです。しかし、30年という歳月と、その間に積み重ねられた当事者たちの努力を知れば、なぜ「外圧」という選択肢が浮上するのか、理解していただけるのではないでしょうか。ここでは、よくある3つの疑問に正面からお答えします。
まとめ:「恥」を「力」に変える
「外圧でしか変われない」という言葉を聞くと、多くの人は「情けない」「恥ずかしい」と感じるかもしれません。
私自身もそう感じることがあります。できることなら、日本が自分の力で変わってほしいと心から思っています。
しかし、日本の法制度改革の歴史を振り返ると、外からの力が変革の触媒として機能してきた事実が見えてきます。
男女雇用機会均等法はCEDAW批准という国際公約がなければ成立が困難だったとされています。ハーグ条約は「G7で唯一の未加盟国」という外交的孤立への危機感が決定打になったとされています。LGBT理解増進法はG7広島サミット(2023年5月)の国際的な視線の中で、同年6月に成立したのです。
外圧は「恥」ではなく、変革のための「力」になり得ます。
- G7で唯一同性婚がないという事実。
- 全国6つの高裁のうち5つが違憲と判断している事実。
- 世論調査で約6〜7割が賛成している事実。
これらを世界に発信することで、国際社会からの関心を高め、政府に変化を促すことができるかもしれません。
イタリアは欧州人権裁判所の判決を「恥」ではなく「変革の正当性」として活用しました。台湾は人権先進国としてのブランドを外交戦略に組み込みました。タイは経済成長のための人権という新しいナラティブを構築したのです。
日本もまた、同性婚の法制化を「国際社会で尊敬されるリーダーであり続けるために必要なステップ」として位置づけることができるはずです。
30年待っても変わらなかった現実に、私たちはもう待てません。世界中の目がこの国に向くまで、書き続けます。そして、「外圧」が「力」に変わる瞬間を、この目で見届けたいと思っています。
よければ、この記事をシェアして、日本の現状を世界に伝える力を貸してください。
筆者より
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
「外圧」という言葉に抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれません。私自身も、できることなら日本が自分の力で変わってほしいと心から思っています。
しかし、30年という歳月は、私たち当事者にとってあまりにも長いものでした。その間に、パートナーと正式に家族になることを夢見ながら、叶わないまま人生を終えた人もいます。病院で「ご家族ですか?」と聞かれ、「違います」と答えざるを得なかった人もいるのです。
私たちは、隠れ場所がほしいわけではありません。陽のあたる場所に、居場所がほしいのです。
この記事を読んで何か感じていただけたなら、ぜひ行動に移してみてください。SNSでシェアする、友人や家族と話題にする、地元の議員に意見を届ける、選挙で同性婚に賛成する政党に投票する。どんな小さな一歩でも、変化につながります。
この記事が、同性婚について考えるきっかけになれば幸いです。
そして、もし共感していただけたなら、この記事をシェアしていただけると嬉しいです。一人でも多くの人に、日本の現状を知ってもらうことが、変化への第一歩になると信じています。
この記事の元になった投稿はこちら
Threadsで見る
参考資料
- 女子差別撤廃条約(CEDAW)に関する外務省資料
- ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に関する外務省資料
- 欧州人権裁判所「オリアリ他 対 イタリア事件」判決(HUDOC)
- 台湾司法院大法官会議「解釈第748号」
- G7広島サミットに関する各種報道
- 渋谷区×認定NPO法人虹色ダイバーシティ共同調査(パートナーシップ制度)
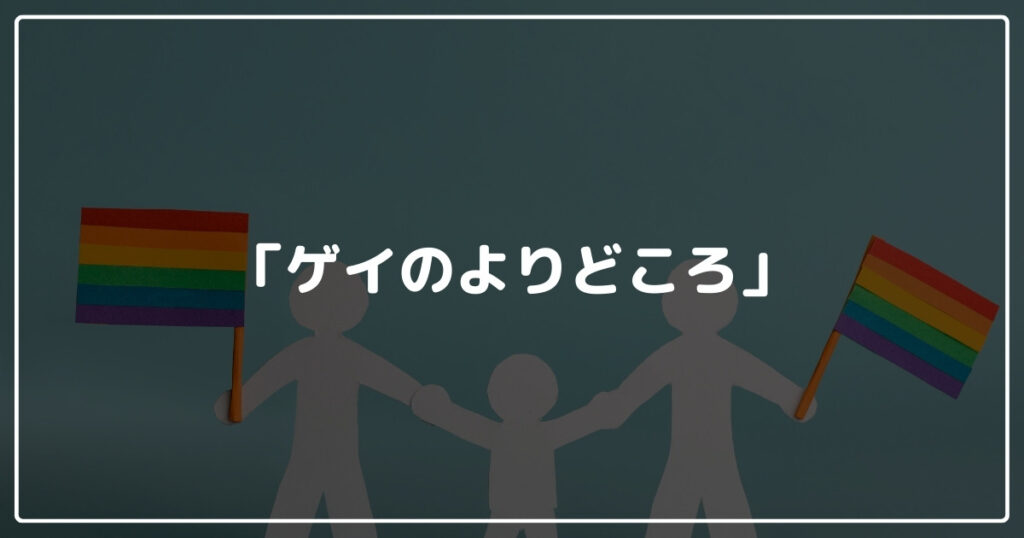


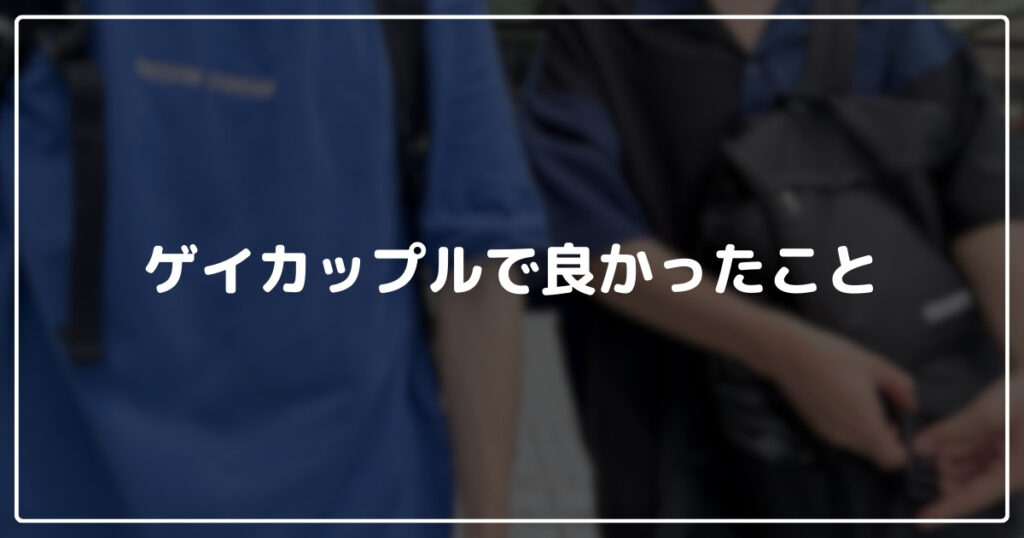

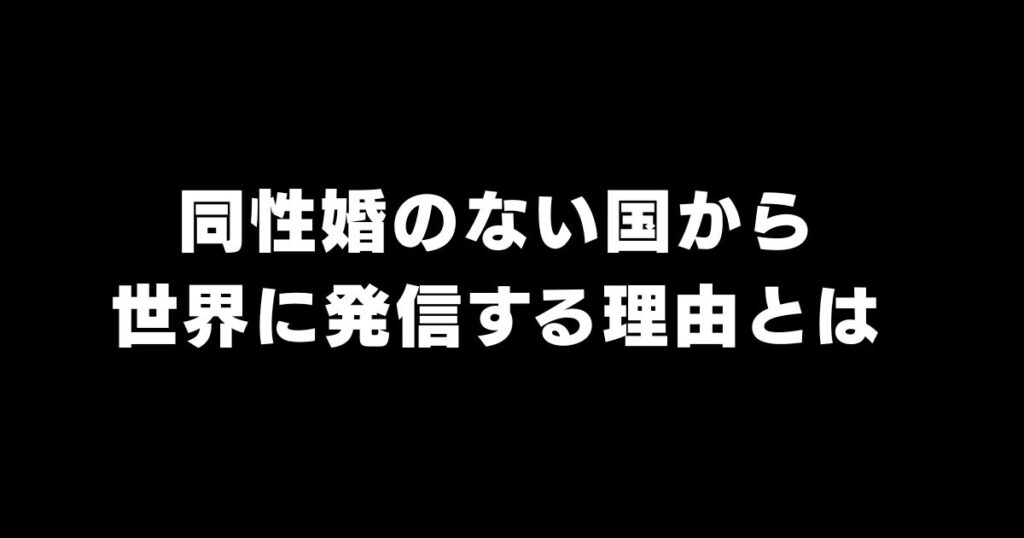
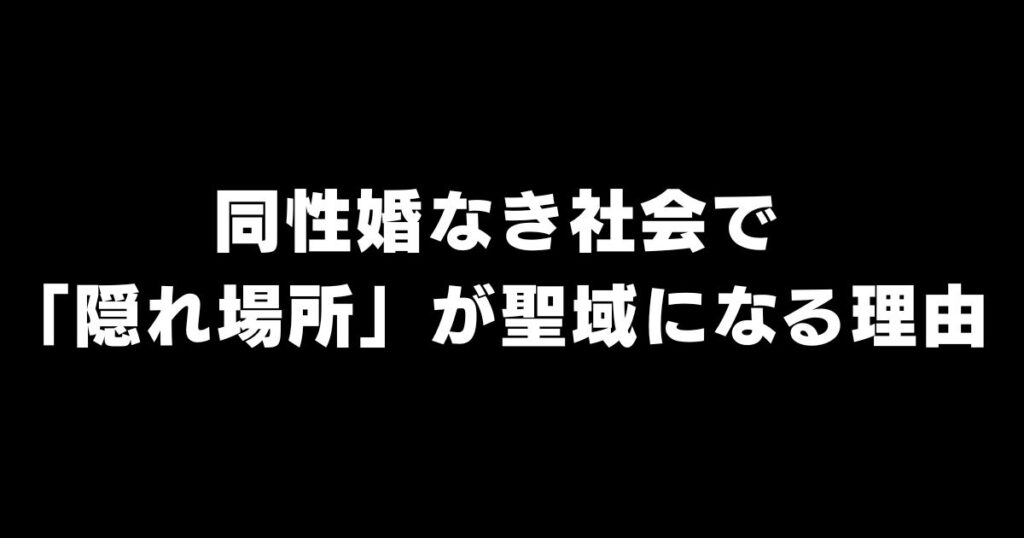

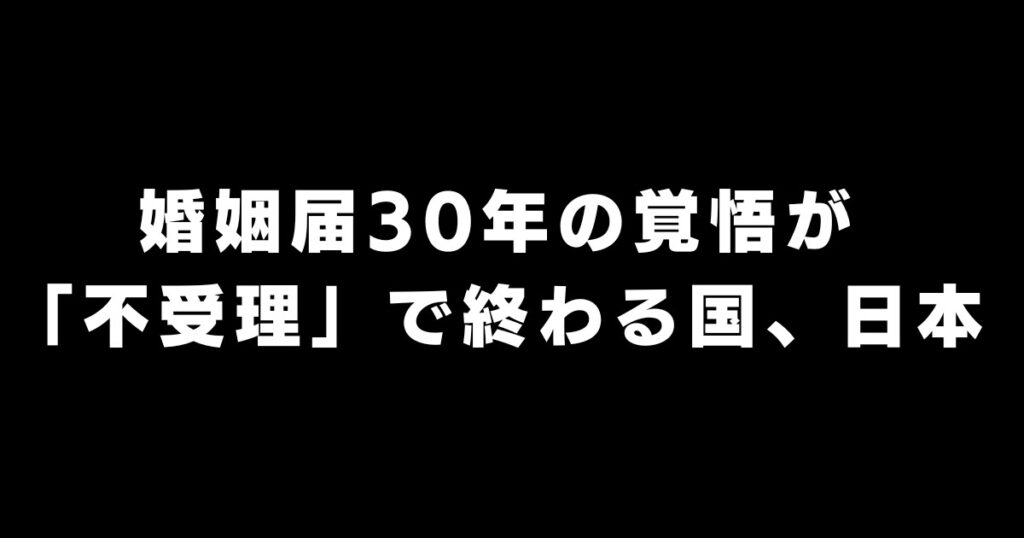
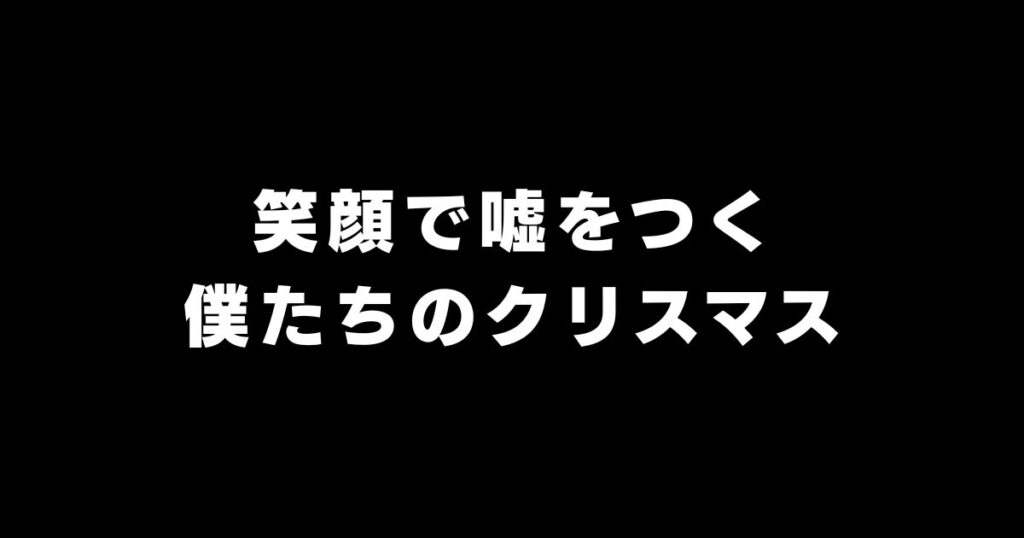

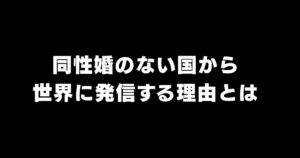
コメントお気軽にどうぞ!